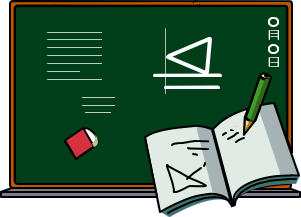
塾長のエッセイ集トップへ戻る
塾長のページトップへ戻る
「教える」とは「知っているものに置き換える」こと
今回は、先週小学生に算数を教えていて思ったことを2つ紹介しようと思います。
私は「教育」を職業にして(大学生時代のアルバイトも含めると)13年が経ちますが、授業の準備をする際に常に念頭に置いていることは「生徒の知っている話に置き換え、生徒の知っている単語で話す」ということです。簡単なことのようですが、これは意外に難しい。なぜなら「生徒の知っている単語」を探すには、その学年までに習った学習内容やそこにいる生徒たちのレベルまで知って(調べて)おかなくてはならないからです。これができない教師(講師)は総じて生徒からの評判は良くない。だから初めて担当する学年・クラスの授業は、その授業時間の少なくとも3〜4倍は準備時間がかかるのです。ちなみに高校生を対象とした予備校の講師(特にトップ講師と言われる人たち)は、90分授業に対して平均8〜9時間の準備時間が必要だそうです。
さて先週、小学2年生は「1000をこえる数」を学びました。最初に「5723」を漢字で書きなさい、という設問から始まります。これは一度声に出して読ませてから書かせれば大丈夫。すんなりとできます(ただしやはり気を遣える講師は「千」という漢字をもう学校で習ったかどうかを確認します)。次にその逆。「四千七百三十二」を数字で書きなさい、という設問。これも恐らく大丈夫です。そしていよいよこんな問題です。
「百を18こ集めた数はいくつでしょう?」…(A)
講師経験がそこそこあれば、パッと見て平均的な小学2年生がこのままの状態で理解するのは困難かな、と分かります(えっ、そう!?と思われるかも知れませんが、自分が8歳だった頃を想像して下さい)。案の定、この問題で生徒の手は止まります。ところが次に講師が発する一言で、生徒の口からしっかりと答えが出てきます。その一言とは…
「じゃぁ、100円玉が18枚あるといくらになる?」…(B)
「えぇと……1800円!?」
(A)の設問では考えをスタートさせることすらできなかった生徒でも、(B)の設問になれば、時間の差こそあれ必ず正答が出てくるのです。これがまさに「学問の実用化」であり、その瞬間こそ「教育者としての達成感」を感じられる一瞬です。
ちなみに小学1年生も少し前に「10がいくつ」という単元を学びましたが、その時に「9+5=14」という計算すらまだおぼつかなかった(ま、一応答えは出てくる状態になってはいましたが)生徒でも、「10円玉9枚と10円玉5枚であわせていくら?」という設問に対して、すぐに「140円」と答えたのには苦笑してしまいました。もしこの問題が「10円玉9枚と10円玉5枚であわせて何枚?」という設問だったら、果たしてすぐに答えが出てきたでしょうか…。
さらに小学校3年生では「10000をこえる数」という単元を学びますが、こちらは普段何万円という金額に接することが少ないためか、お金の例を挙げてもうまくいかないことが多いのです。「1000円札24枚でいくら?」と問いかけてもなかなかパッとは出てこないのです。よって講師は別の例を模索することになります。教育って奥が深いですね…。
もう1つ、小学5年生の「割合」の授業から考えさせられたこともあったのですが、長くなってしまいましたのでそちらは次回に紹介します。
はなぶさ通信 第74号(平成21年1月20日発行)より