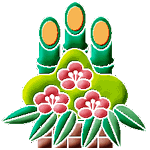
美しき日本…の言葉
阿倍元総理大臣が「美しい国、日本」という言葉を使ったのは、平成18年末でした。その阿倍内閣は、教育改革に取り組むということで、小学校の授業時間の10%増とか、週5日制を見直して土曜日に半日授業復活、などの改革案を出しているそうです。私としては土曜日の授業は廃止するべきではなく、またゆとり教育にもあまり賛成ではなかったので、今回の改革案の方向性は間違っているとは思いません。しかしいったん変えたシステムを元に戻すということは、お金だけではなく様々な面で多くの機関や人間に迷惑をかけることになるので、今後はよく考えてから改革を推進してもらいたいものです。
しかも、たとえば消費税を3%から5%に上げたものを再び3%に戻すというような改革(これも大変でしょうが)と大きく異なるのは、対象が商品ではなく人間(子供)であるということ。週5日制でゆとり教育を実施していたこの何年かの生徒達は様子見の実験台だったのか、ということにもなってしまいます。
また教育現場にいた人間として言わせてもらえれば、土曜日に授業が復活するということになれば、生徒達(特に小学生)のブーイングは恐らく大きなものになるでしょう。それを受け止めるのは文部科学省ではなく、現場にいる教師です。こういった事もよく考えてみてほしいと思います。
さて、日本を美しくするのは政治に期待するとして(まぁ無理でしょうが)、唐突ですが日本の「言葉」は本当に美しいと思います。先週小学6年生の日本語の授業で日本の風習についての授業をしました。時間にすれば20〜30分間くらいだったと思いますが、十二支の話と、1月〜12月の日本古来の呼び名について勉強しました。睦月(むつき)、如月(きさらぎ)、弥生(やよい)、…という言葉は、単純に数字を当てはめただけの呼び名とは違ってどこか美しい。
そこにはたとえば、「1月は、今年も仲睦まじく(仲良く)暮らせるように」とか、そういったいろいろな意味も含まれているのだけれど、それだけではなく、声に出した時の「音の響き」にも素敵な要素が存在するような気がするのです。「やよい」というヤ行の音には何か春らしいイメージとか、もちろんまったく科学的でも論理的でもないのだけれど、日本語の美しさというのは「聞いて」味わうこともできるものだなぁと思いませんか。
先日何かの本を読んでいた時に「灯ともし頃(ひともしごろ)」という単語に出会いました。家々に電灯がつき始める「夕方時分」を表す単語だそうですが、こんな素敵な日本語、他にもたくさんあるような気がします。時代の流れに逆らっているのかも知れませんが、ぜひこういった単語を忘れることのない「日本」であり続けてほしいと思います。
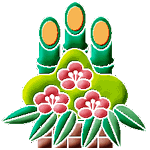
はなぶさ通信 第23号(平成19年1月23日発行)より