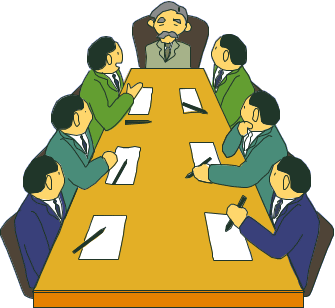
塾長のエッセイ集トップへ戻る
塾長のページトップへ戻る
私の「人物判定法」
他のエッセイで「夢の期限を持とう」というテーマのもとに、あるベンチャー企業の社長の社員採用法について紹介しました。今回は私自身がどのような視点で他人を見きわめているか、少しだけ紹介しましょう。まぁ自分自身の方針を自分で記述するわけですから、多分に偏った話になるかもしれませんが…。
私には「これさえできていればそれでよし(会社で言えば即採用!)」といった単純明快な基準はありません。が、「これができない人は絶対に信用しない(会社で言えば即不採用!)」という基準が2つあります。
その1つは「時間を守る」ということ。当たり前のことなのですが、100%いつでも厳守するというのは意外に難しいものです。道が渋滞していた、道に迷っていた、など理由はいくらでもありますが、私の中ではどれもすべてペケ! しかも「遅れます」という連絡がなかった場合は、たとえ1分の遅刻でも即ペケ! これは「約束の時間を守る」という意識が足りないのです。つまりその約束を「軽いもの」として見なしているということにほかなりません(この仕事をそんな風に見ている人は絶対に採用したくないですからね)。自分にとって非常に大事な約束なら、渋滞や道に迷うことも予測して(場合によっては前日の同時間帯に下見までして)出発するはずです。だから私は会合の1時間前に到着してしまうこともざらにあります(特に遠方に出かける場合)。でもそれはそれで現地に到着してからどこかで時間調整をすればいい。
今までいくつかの会社(または学校)に勤務してきましたが、決められた時間の会議に遅れたことはないし、(私は現場優先主義なので)お客や生徒への対応で絶対に会議に間に合わないと分かっている場合は、あらかじめ議長(または校長)にその旨必ず伝えていました。自分の仕事のキリをつけるために遅れたことは1分たりとも、1回たりともないはずです。
ところが、(人数が多い会議ほど)遅れて来る(しかも平気で)同僚が非常に多い。「仕事が多くて忙しい」なんて言っている(言い訳している)人もいましたが、たくさんの仕事を抱えている人でも、ちゃんと定刻に着席している人はいつも着席している。そして遅れる人は常に遅れて来る。私はいつもその様子を眺めながら、どの人が信用に足る人でどの人が時間を守れない人か、を考えていました。今でもどうしてもお願いしたい重要な仕事を依頼する場合には、信用できる人のところへ持っていきます。
生徒についても私はほぼ同じように見ています。塾は「自分から望んで」来る場所だから、法律的に言えば「遅れて来る権利」もあるのかも知れません。が、それで平気な顔で遅れて来る生徒に対しては「この子はきっと将来苦労するだろうなぁ」と心の中で思っています(まぁだいたいそういう生徒は、経験上成績も期待するほどには上がりませんが)。ただ、子供の場合は、本人ではなく送ってくる家族の方がそういう考え方だからという場合もあるので、あまり強くは指導しきれない部分もあるんですけどね。
「見きわめ法」はもう1つあるのですが、そちらは続編で紹介します。
はなぶさ通信 第67号(平成20年10月14日発行)より